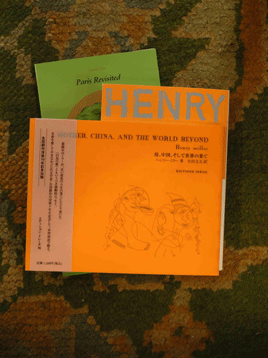
第3回:ヘンリー・ミラー『母、中国、そして世界の果て』
「母は僕の顔を優しく覗き込んで言った。『こちらへ来てわかりましたが、私たちが地上で信じていたほど書物は重要なものでもないのですよ。此処には新聞も雑誌も本もありません。ここでは会話自体が本を書くことであり、本を読むようなものなのです。頭痛に悩まされることもなければ、お腹痛になることもありません。日々、私たちは人生についての広い視野を手に入れ、自分自身に対しても他人に対しても、より寛大に、より穏やかになっていくのです』
(中略)
母の言葉はますます僕を感動させた。かつては鉄のダンベルのように僕に重くのしかかった母の言葉が、いまは知識の泉のようだった。」(「母」)
ヘンリー・ミラーは1891年、ドイツ系アメリカ人である父ハインリヒ・ミラーと母ルイーゼ・ミラーの息子として生まれたが、特にヘンリーにとってルイーゼ、すなわち「母」という存在は常に否定的なものであった。「母親の愛情というものをまるで知らない」ままに憎しみの中に育ち、作家として成功して以降も生涯それを母に認められることはなかったという。その言葉のみならず存在自体もまた「鉄のダンベルのように僕に重くのしかかっ」ていたのである。
今回ご紹介するのは、最晩年の1976年、84歳にして記した『母、中国、そして世界の果て』という短編集の「母」という作品である。「こちら」というのは死後の世界のようなところで、物語は「僕」がその場所で「母」と出会うところからはじまる。その世界では願ったことは叶えられるため物質的な欲望からは開放され、そこに留まっている人間には誰にでも会うことができる。「母」がその世界から去っていくまでの間の「僕」との対話、それがほぼ全編を占めるのだが、冒頭の引用部はちょうどその真ん中あたりの箇所だ。すでに死を予感しながらも書き続けたヘンリーの最期の希望、特に生涯知ることがなかった「母」の愛情に対する希望のようなものが、全編を通して切なくも鮮やかに描かれている。
ヘンリー・ミラーは職を転々とし、結婚と離婚を繰り返し、大胆な性描写や社会に対する批判精神を、難解な表現で描いた作家、というのがごく一般的な認識だ。そのイメージを強くしたのは、事実上の処女作であると同時に代表作でもある『北回帰線』(1934)である。60年代にアメリカで発売された際に、その過激な性表現で発売禁止になったことで、余計にその名を人々に知らしめることとなった。
その『北回帰線』が生まれる数年前、ヘンリーが出会った女性がアナイス・ニンである。アナイスは『小鳥たち』『近親相姦の家』などの作品でもよく知られているが、最も有名なのはその膨大な日記だろう。特にミラーとの日々は『アナイス・ニンの日記 1931〜34―ヘンリー・ミラーとパリで』(ちくま文庫)という題で邦訳もされており、それを読めばパリで出会った40歳のヘンリーと20代後半のアナイスがいかに愛し合い、アナイスの存在がヘンリーに『北回帰線』を書かせるのにどれだけ大きな役割を果たしたかがわかる。『巴里ふたたび』は、そのアナイスが後年、15年振りに訪れて思い起こす当時のパリの姿を描いたものだ。
そして『母、中国、そして世界の果て』という、『北回帰線』からは想像もつかないほど易しく感動的な掌編を書いた4年後の1980年、ヘンリー・ミラーは本当にこの世を去った。彼の死後の世界が彼の想像したとおりのものであったかどうかを知ることは誰にもできないが、もしこの物語に描かれているような世界に彼が今なおいるのだとしたら、ぼくは死後真っ先に会いにいきたいと思う。(文・内沼晋太郎)
ヘンリー・ミラー『母、中国、そして世界の果て』(エディション・イレーヌ)
<関連書籍>
ヘンリー・ミラー『北回帰線』(新潮社)
アナイス・ニン『巴里ふたたび』(エディション・イレーヌ)
ご紹介の書籍は、GRAVITAS&GRACE 銀座店でお買い求めいただけます。